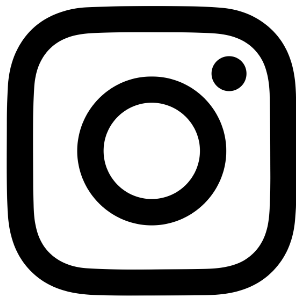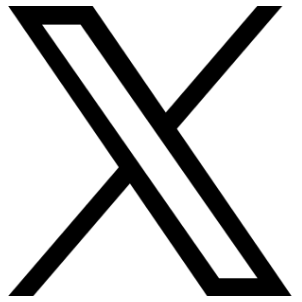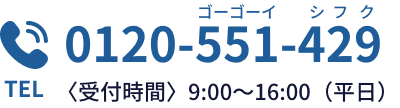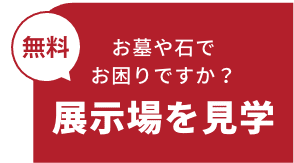2025.5.21
【1】戦争の中で生まれた社長 -イシフク会長 望月威男物語

昭和十七年、冬。朝鮮・元山の港町に、ひとりの男の子が生まれた。名を威男(たけお)という。
父・松二は、戦争の影が色濃くなる中、日本の植民地だった朝鮮で大東鉱業の炭鉱所長を務めていた。母・ツネは平壌の病院で看護婦長として働いていた。二人とも、異国の地で懸命に生きていた。

(元山の大東鉱業時代。威力の父・松二と母ツネ・兄と姉)
しかし、戦争はすべてを変えた。昭和二十年、終戦とともにソ連軍が侵攻し、日本人の多くが捕虜となった。松二も例外ではなく、家族もまた危険にさらされていた。捕虜収容所では、婦女暴行が始まっていた。収容された日本人女性たちは震えながら身を寄せ合い、男性たちも次々とシベリアへ送られていた。
「シベリアへ行けば、生きて帰ることはできない。」
松二は、そう確信した。ここに留まることは死を意味する。死を半分覚悟し、脱走を決意した。
深夜、見張りが交代する一瞬の隙を狙い、家族を連れて暗闇の中を駆け抜けた。銃声が響くたびに胸が締め付けられた。何人もの仲間が倒れるのを横目に、それでも足を止めることは許されなかった。
ツネは幼い威男をしっかりと抱きしめた。寒さと恐怖に震える小さな体。母の胸に顔を埋め、何も見えないふりをするしかなかった。夜を徹しての逃避行の中、喉の渇きと空腹が家族を襲った。まともな食事も取れず、道端の草を噛みしめることもあった。威男の姉・紀美子は弱音を吐かず、弟の手をしっかりと握りしめていた。
「あと少しだ……」
松二は自分に言い聞かせるように呟いた。京城(現在のソウル)を目指し、さらに釜山を経由して日本への帰還船に乗る。
十一月二十六日、博多港。ようやく日本の地を踏んだとき、家族の手元に残っていたのはわずかばかりの荷物と、未来を切り拓くための覚悟だけだった。
「ここからまた、一からやり直す。」
父・松二の決意は固かった。
威男はまだ幼く、戦争の意味を深く理解することはできなかった。ただ、母のぬくもり、父の険しい顔、道中で流した涙だけは、心に深く刻まれていた。
この時、彼にはまだ知らなかった。これから先、石とともに生きる運命が待ち受けていることを。

(元山から博多まで1080km。決死の逃亡ルート)